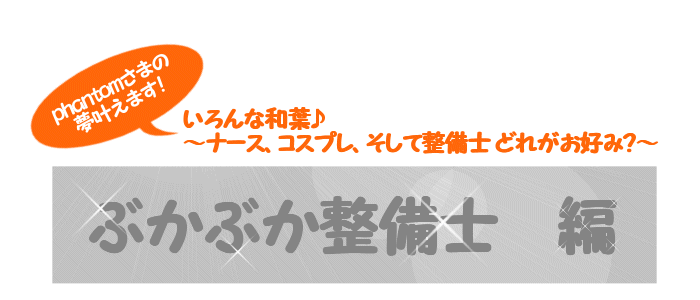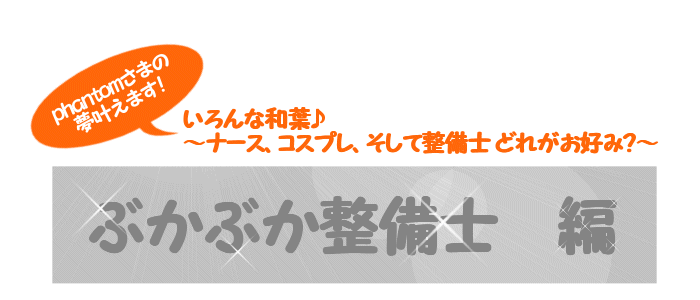
| 「なぁなぁ、おじちゃんの車・・・・・銀色でピッカピカで、かっこえーなぁ。」 「そーやろ! おとんの宝物なんや。休みの日はな、いっつも車洗ったり拭いたりしとるんやで。」 「そーなんや。宝物、大事にしてるんやね! 車も嬉しいやろな。いっつも綺麗にしてもろて。 ええなぁ・・・・・銀色のピッカピカ。」 寒い寒い北風が吹きつけ、落ち葉がかさかさと風に流され、つい猫背になってしまう この季節。 平次は自分の愛車の前で、呆然と立ちすくんでいた。 「へ・・・・へこんどる・・・・。」 力の抜けてしまったその体は、突然の強い風にあおられフラリとよろけた。 駐車中に当て逃げされた車を、知り合いに紹介された修理工場に持ち込むため、 平次は右側のドアが大きくへこんだままで、気の乗らないドライブをしていた。 かなり裕福な家庭で育ったとはいえ、平次の両親は簡単に車を買い与えてくれる 訳ではない。 アルバイトをして頭金を貯め、親に保証人になってもらい、やっとローンで 購入した大切な車。 幼い頃仲の良かった女の子が、大きな目をキラキラさせて、父の車を見てよく言っていた 「ええなぁ、銀色のピッカピカ・・・・」 その言葉が忘れられず、平次が初めて買ったこの車もシルバーメタリック。 その女の子は小学校に上がる前に、父親の転勤で引っ越してしまった。 今でも時々思い出す、別れの時のあのシーン。 「かずちゃん!」 「へーちゃん!」 と抱き合い2人で大泣きした。 色の白い可愛い女の子の目は、ウサギみたいに真っ赤だった。 かずちゃん、どうしてんやろ・・・・ 15年も前の出来事だったが、平次は今もかずちゃんの事を忘れた事など無い。 これが彼の今も続く初恋だった。 そんなことを考えながらのドライブは、懐かしく甘酸っぱい気分になり 鼻歌の1つも出そうになったが、目的地の看板が見え始め 平次は現実を思い出し、大きく溜息をついた。 修理工場に到着し、出迎えたのは、社長の関根だった。 「服部さんですか? 府警の大滝さんから聞いとります。」 「どうも服部です。派手にやられてもーた・・・・修理に時間かかるんかな?」 「あー、これは・・・・微妙な感じやなぁ。ほな今、担当を紹介しますわ。 めっちゃ腕が立ってな。仕事も丁寧やし。うちの自慢の新人ですわ。」 「新人さん? 大丈夫なん?」 「そりゃ、もちろん。私もちゃんとチェックするんで安心しとってください。 おーい、遠山―! 遠山おるかぁ!」 後ろから軽い足音が近づいてきた。 振り返ると、逆光になり顔は見えないが、やけに小柄な影がこちらに向かってくる。 白い作業着はあちこち油で汚れ、手も足も何重にも裾を折り返し、ダボダボなツナギは きゅっと締められたベルトで辛うじて着ているという感じだった。 まぶしくて額に手をやる平次。 だんだん目が慣れて、やがて見えてきたものが信じられず、 ポカンと口を開けたまま固まってしまった。 長い髪を後ろで1つにしばり、化粧っけの無い、頬にまで油をつけたままで にっこり笑ったその顔は・・・・・ 一目でわかった。 幼い頃の笑顔のまま綺麗になった、かずちゃんだった。 「こんにちは、遠山です。」 「ど、どうも。服部や・・・・服部平次・・・・」 「・・・・?? 服部さん。アタシが担当させてもらいます。 これから状態を調べて、修理の箇所とか時間とか、あと簡単な 見積もり作りますので。明日また来ていただけますか?」 「・・・・はい・・・・」 平次はその後の会話も思い出せないほど動揺して、気がつくと修理工場を 後にしていた。 「かずちゃん・・・・」 まさかこんな所で・・・・ 冷たい風にあたり、徐々に現実を受け入れると今度は、 寒さを感じなくなるほど気分は高揚してきた。 あんなに腹の立った当て逃げでさえ、今では感謝したい位だった。 夢にまで見た感動の再会。 しかし、彼女は覚えていないようだった。 フルネームで名乗った自分を、不思議そうに見返してきたあの瞳。 少なからずショックを受ける平次だったが、彼女が自分を思い出し 涙々の再会を演出できるよう、日頃から鍛えている心と体をフル回転させ その方法を考え始めていた。 その日の夜。 自室でくつろぎ、昔のアルバムを眺めている平次の携帯がふるえた。 「はい。」 「服部さんですか? 関根自動車工業の遠山です。 修理の件ですが、実はダメージを確認するためにドアの内張りを外してみたところ、 かなり奥までやられとって、ドアの安全性にも問題が出てくる状況なんです。 これやったら板金だけじゃ済まないので、ドア自体を交換した方がいいんですが・・・」 「そーなんや。」 「ただ、ドアの交換ともなると時間も費用もかかってしまうので・・・・・ ご了承いただかないと、作業もドアの発注も出来ないと思いまして。」 「あー。今な、財布厳しいんや。困ったな・・・・」 「やったら、新品のドアやなくて中古のドアを探しますか? 時間はかかりますけど。」 「ほな、中古のドアで頼んますわ。」 「はい。そやったら急いで探しますので。」 「おおきに。ほな明日午前中、状況見にそっち行きますわ。」 「はい。ほなお待ちしてますので。」 知らず知らずのうちに緊張していたのか、ふーーーーっと息をついた平次。 ふと時計を見ると、すでに9時をすぎている。 彼女は仕事でやっているだけとわかっていたが、 こんな時間まで冬の寒空の中、吹きっさらしの工場で自分の車を 見てくれていた姿を思い、じんわりと平次の心は温かくなった。 約15年ぶりの再会に、大きく心が動いた1日も終ろうとしている。 彼女は今頃何をしているのか・・・・・ そんなことを考えながら、 平次は明日、朝一で修理工場に行くために、 久しぶりに目覚まし時計をセットして眠りについた。 翌朝、この冬一番の冷え込みだとTVの天気予報が伝えている頃。 平次は目覚ましのなる3分前にむっくりと起き上がった。 いつものような寝起きの悪さはない。 窓を開け、身が引き締まるほどの冷たい空気を吸い込み、気合を 入れるために両手で頬をパンパンと叩いた。 自分の車の修理というのはすっかり忘れて、目的は初恋のかずちゃんに 会いに行くことになっていた平次。 いつもより念入りにヒゲをそり、髪を整える。 いつもピョンと、とんがりが出てしまう髪のクセは今日も直らずにいた。 修理工場の朝は早い。 8時にはシャッターを開け放ち、作業を始める。 夏は灼熱の日差しのなか、冬は凍えそうに吹雪いていても 冷暖房をつけることなく外気の中で、ただ黙々と車と向き合う。 ほこりやススや油にまみれながらする作業は、とても女性向きとは言えない。 しかし和葉は、子供の頃からの車への憧れから、迷う事無くこの職業に就いた。 昨夜、平次に連絡した後、取引のある自動車部品を扱ういくつかの工場にドアの在庫を 問い合わせしていた和葉。 答えはすべてNOだった。 ただ同じ車の同じ色というだけでは、ぴったり合うものは見つからない。 車両の色番号は同じでも、年式や保管場所の状況などによって 色は変わってくる。 中古車と新車では色も輝きも全く違うものだ。 その辺を考慮して早めに探し始めたのだが、簡単に条件の合うものは なかなか見つからないので、時間がかかってしまう。 急がなくては・・・・・ 今日3件目の中古部品屋に問い合わせるために、和葉は受話器を上げた。 「おはようさんです。」 工場に平次の大きな声が響き渡る。 隣の事務所でそれを聞いた和葉は、平次が気付くように大きく手を振った。 それに気がついた平次は、たったそれだけの事で嬉しくなってしまう、 まるで恋する中学生のような自分の中の可愛らしい部分を思い、小さく笑った。 事務所に入り、和葉の電話が終るのを待つ平次。 どうやら目当てのドアはなかったようで、平次に背中を向けたまま溜息をつく和葉。 しかし、くるりと振り返った時はもう笑顔だった。 「おはようございます、服部さん。早いですねー。」 「おー、おはようさん。」 「実は昨日あれから、県内の中古部品を扱う工場に、同程度のドアの在庫を問い合わせとる んですが、なかなかなくって・・・・ もちろん急ぎますが、もう少し時間をいただけますか?」 「まぁ、しゃーないな。アンタも頑張ってくれとるんやし。ただな、状況が知りたいから 1日1回は連絡よこしてくれや。オレも気になるしな。」 もちろん車も気になるが、それは和葉と毎日話をするための口実にすぎない。 「ほんなら車の方、見せてや。」 「はい、こちらです。」 それなりの大きな工場の隅っこに、平次の車はひっそりと置いてあった。 まだ作業に取り掛かれないのだから仕方が無い。 「服部さん、車大事にされとるでしょ。見てわかります。」 「そーやで。良ぉわかったな、アンタ。自分の車やから洗車なんかは当然やけど、オイルやら細かいパーツはマメに変えとるし。あと丁寧な運転を心がけとる。」 「ちょっとここまで運転させてもらいましたけど、クセのないええ車です。 シルバーメタリックもピッカピカやし。」 平次は和葉を見つめながら、大事にしていたあの言葉を口にした。 「そーやろ。昔な、仲良かった子が銀色の車好きやったん。 オヤジが大切にしとった車見て、えーなぁ、銀色のピッカピカっていつも言っとってな。 自然とオレもすっかり洗脳されとったわ。自分の車もシルバーに以外考えられんかったからな。」 和葉の表情が変わった。 「え・・・・銀色の・・・・ピッカピカ、ですか!?」 「そうや。アンタ何か知っとるんか?」 「いえ・・・・あの・・・・昔ちょっと・・・・」 「ほーか。」 和葉は子供の頃言っていた、銀色のピッカピカという言葉が、まさか目の前に立つ、 この男の口から出てくるとは思わず、内心かなり動揺していた。 幼稚園の頃だったか・・・・ いつもピッカピカに輝いている、かっこいい大好きな車があった。 そして、その車を大切にしているおじちゃんが手入れをしているのを、 いつも隣にいた大好きな男の子と一緒にそれを眺めていた。 その男の子は、今何をしているのだろう? ずっと会いたいと思っていた。 そう、名前は・・・・・確か・・・・・けいちゃん?・・・・いや、へーちゃん、だった。 あれ? この人の名前は・・・・ 和葉はそんなことを思い出しながら動揺を悟られぬよう、ダメージを説明しだした。 ドアを開け仮止めしてあった内張りをはずし、問題の部分を指し示した。 しかし、かすかに震える声は止められずに・・・・ 「これです。あの部分の損傷が、ドア全体の強度に関わってくるので 交換をお勧めしたんです。」 「あー、なるほどな・・・・」 先ほどの「銀色のピッカピカ」という言葉に反応した和葉を見て気を良くした平次は、 説明する和葉と手がふれてしまう位近くにしゃがみこみ、間近で和葉を観察し始めた。 綺麗に洗濯してある白いツナギも、よく見るとうっすら油のしみが残っている。 手足を何重にも折り返し、男物であろうダブダブのツナギを着ている、 そのアンバランスさにドキリとする平次。 そんな和葉の鎖骨がチラリと見えて、妙な色気を感じてしまい平次はあわてて立ち上がった。 「よーわかったわ。ドアの事は、アンタを信用して全てまかせる。 アンタが納得するまでやってくれや。連絡だけマメに入れてくれればええよ。」 「はい。わかりました。」 こうして1日1回、いつも夜の9時頃に和葉から連絡が入るようになった。 初めは用件だけだったその電話も、1週間を過ぎるとかなり打ち解けた雰囲気になり、 以前からの友人のように冗談を言い合えるようになっていた。 時々フラリと差し入れを持って現れる平次の姿は、あまりに自然で 誰もが旧知の仲と思い込んでいたほどだった。 そして11日目、夜。 和葉からのいつもの電話を、工場近くのファミレスで受けた平次。 近くにいるからと、偶然を装い会いにいくつもりだったが、 その電話の内容に、ついにその日がやってきた事を知った。 「あ、服部さん? あったよ、あった! ドア、見つかったんや! もう発注したから、明日届くんよ!」 「・・・・ほーか・・・・」 「ドア以外のところは終っとるから、明日夜には引渡し出来るよう頑張るわ。そんでな、」 吸っていたタバコを乱暴に灰皿に押し付け、平次は和葉の言葉を遮った。 嬉しそうな和葉の声を聞き、平次のイライラがつのる。 「なぁ、今、出先なんやけど、そっち寄るわ。15分位で行くから。」 「え?」 とまどう和葉の声が聞こえたが一方的に電話を切り、冷め切ったコーヒーを一気にあおり、 平次はファミレスを出た。 和葉は毎日の電話の中で、しきりに時間がかかって申し訳ないと言っていた。 だから、ドアが見つかり作業ができると喜んでいるだけなのに。 このつながりが終ってしまう事が、そんなに嬉しいのか・・・・・ そんな事を考えてしまう平次は、心の中の不安と怒りを必死に打ち消していた。 今日乗ってきたのは、和葉が「銀色のピッカピカ」と言っていた、あの車。 平次の父は、初めて買ったその車を、本当に本当に大切にしていた。 今となっては古めかしいその車も、手入れをかかさず、もちろん今でもしっかり乗れる。 マニア受けしそうなその車には GT−R とあった。 今まで、平次には1度も運転させてくれなかったその車を、一晩貸してくれと 父に深々と頭を下げ、ようやく借りる事ができた。 平次の運転技術は問題ない。 むしろ上手いほうだと、何度も同乗している父も理解はしていた。 ただ、宝物をいくら息子とはいえ簡単に貸したくなかっただけで、 珍しく本気で頭を下げる平次の気持ちを尊重して、首を縦に振った。 数台しか止まっていないファミレスの駐車場で、ひときわ目立つ父親の愛車。 平次はその姿をしばらく眺めて、「頼むで・・・・」と小さく呟き車に乗り込んだ。 澄んだ夜空には星が瞬き、平次は何分後かの自分の状況を思い、 ガラにもなく祈ってみた。 修理工場のシャッターは閉まっていたが、中から灯りがもれていた。 平次は何枚もあるシャッターの隣の小さな扉をたたいた。 「はーい、服部さ・・・・」 出てきた和葉は、平次の背後にある車を見て立ちすくんだ。 「これやろ? 銀色のピッカピカって。」 動けなくなった和葉の瞳から、はらはらと涙がこぼれた。 「な・・・・なんで・・・・ここに?」 「オヤジの車、借りてきた。」 「本当に・・・・あの車なん?」 「おう。」 「アタシ・・・・この車が大好きで。この車を大切にしているおじちゃんの 笑顔が好きで。それで・・・・一緒に見ていた男の子が好きで・・・・」 そう言いながら、ゆっくりと車に近づく和葉。 「その男の子っちゅうのがオレや。オヤジは今でもこの車が宝物でな。 今日初めてオレに貸してくれたんや。」 「あの頃から、車を大事にしているおじちゃんのお手伝いをしたいと思ってて・・・・」 「オヤジかい・・・・」 「ちゃうよ。車を見つめる瞳が本当に優しくって、そんな車を大切に思う人たちの 手伝いをしたいと思って、この仕事についたんや。」 「・・・・多少古びたかもしれんが、あん時と変わらんやろ?」 平次に背を向けていた和葉が、ゆっくりと振り返った。 「本当に、へーちゃんなん?」 「そーやで、かずちゃん。」 再び和葉の瞳はうるみだし、それを隠すかのように、また車に向かい合った。 「会いたかったんよ。この車にも、へーちゃんにも・・・・」 平次は黙ったままゆっくりと和葉の横に並び、おそるおそる、その小さな手を握った。 幼い頃は同じような大きさだったその手は、会えなかった時間を表すかのように 大きくなった平次の手の平に、すっぽりと納まってしまった。 「何でオマエ、会ってすぐオレだって分からんかった? オレは一目でかずちゃんやって気ィ付いたで。」 「・・・・・」 「コラ、答えろ和葉!」 「え?・・・・和葉って・・・・」 「そりゃ、かずちゃんって呼ぶ年でもないやろ? オレら。 オマエもへーちゃんやのうて、平次、やからな。」 「平次・・・・」 「おー・・・・何か照れるな」 赤面した平次を見て、涙を拭き笑い出す和葉。 それにつられて平次も笑い出した。 2人の笑顔は幼いときと変わらずに・・・・・ 「おめでとさん。これでオマエは、ガキの頃から憧れとったこの車専属の整備士や。 相当腕がええって社長も言っとったしな、オレがオヤジに推薦したる。 今度そのツナギ着たまま、オレんちこいや。」 「えー、これで!?」 「そーや。オヤジ達、びっくりすんでー! あんときの和葉が、こんなガテン系の女になってたんやから。」 「ガテン系って何やの! これがアタシの制服や!!」 「制服〜? そーいうんはナースとか、スッチーとか、ミニスカポリスとか、 色っぽいモンを言うんや。オマエのツナギは、ぶっかぶかでガキが大人モンの服着とるみたいやで。」 「へーーえーーじーーィ」 振り上げられた和葉の腕をつかみ、優しく抱きしめる平次。 「これからゆっくり、15年分の空白をうめていこうや、和葉。」 「うん・・・・平次。」 2人はゆっくりと目を閉じた。 余談だが。 和葉の言葉どおり、翌日の夜に引き渡しとなった平次の車は予想以上の出来上がりだった。 元の姿と全く変わらない事に感激した平次が、薄汚れたツナギのままの和葉を お姫様だっこして無理やり愛車に乗せ、さらって行ってしまった。 寝屋川方面に向かったようだが、行き先は誰も知らない。 END |