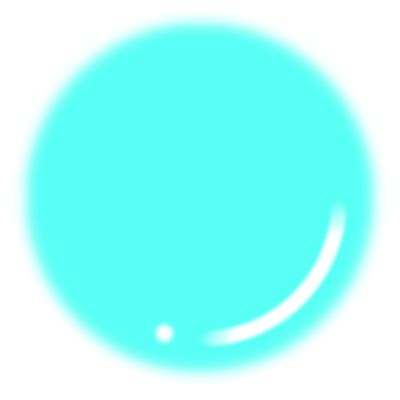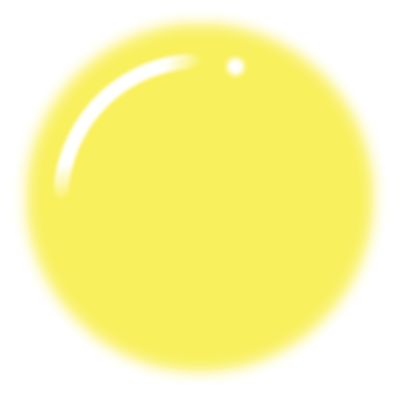| 改方学園高校、数学教師。小嶋。 東京出身、26歳独身。現在、彼女募集中とのこと。 現在2年B組、ちなみに服部平次のクラスの担任。 身長180センチ弱。水泳部顧問。小学生の頃から水泳を続けているそうで、肩幅が広く引き締まったいい身体をしている。 生徒から人気があり、ひそかにファンクラブがあるらしい。 そんな小嶋の噂が、学校中を駆け巡った。 「小嶋は、隣のクラスの遠山和葉がお気に入りらしい。」 その噂の遠山和葉といえば、あの服部平次の自称「幼馴染のお姉さん役」として有名であった。 一年の時は平次とも同じクラスで、その小嶋が担任だった。 今は2年A組。 そんな和葉のことを、やかましいと言いつつ大切にしているのが服部平次。 高2になって初めて和葉とクラスが別れたが、休み時間になると何かとA組に現れては和葉をからかっている。 もっとも事件だ依頼だと、学校を休みがちではあるが。 「もー平次、今頃学校に来て、教科書一式借せって何やの?」 「あ? 今朝6時に事件に呼ばれてな、終わったら学校行くつもりで 制服で行ったんやけど、鞄忘れた。えーやろ、減るもんやないんやし。」 「減ります〜。ちゅうかアンタ、人の教科書に落書きせんといて! 小嶋の足はクサイとか、小嶋は将来ハゲるとか。アホな小学生みたいな事・・・アンタ、担任なのに。」 「フン、小嶋なんぞが二年連続担任になりよって・・・もうアイツとは関わりとうなかったんじゃ、ボケェ!いつまでたっても標準語しゃべりよって、何年大阪におるんや。 きっしょいんじゃ、アイツ」 「アホ、何言うてんの! 先生、アンタのことちゃーんと理解してくれてるやん。 いろいろ配慮してくれとるんやし、もっと先生のこと尊敬しなきゃあかんよ。」 「尊敬ってオマエ、小嶋の味方か?」 「敵とか味方やなくって、去年の担任やし? ほら、アタシ去年クラス委員やったから、先生がアンタを心配しっとったの よくわかるんよ。」 小嶋の噂をすでに耳にしている平次にとって、おもしろくない事この上ない。 苦虫を噛み潰したような顔をしている。 あの噂は、多分・・・真実。 いつも和葉を後ろから見守っていたからこそわかる、小嶋が和葉に向ける視線の意味。 もっとも、当の和葉はそんな事気付いていないが・・・ そして周囲の人間も、「誰々が和葉を気に入っている」なんて噂は日常茶飯事で全く気にしていない。 今までも新任教師や、臨時講師、先輩から後輩まで、いろんな噂が出ては消えていた。 結局、誰と噂になったところで、例の特別な幼馴染がいるのだから・・・と。 しかし、小嶋が相手の噂だけは何度も出てはいたのだが、聞き流すことに慣れてしまった人々は、すぐに忘れてしまった。 ある日の放課後。 前日の授業の途中で事件の依頼が入り、鞄を置いたまま飛び出して行ってしまった平次。 丸一日以上たってやっと解決して、テストが近いので仕方なく学校に鞄を取りに戻って来た。 この時間なら、まだ和葉は残っているだろうと、いつものように何のためらいもなくA組のドアを開けた。 「おーい、和葉おるか?」 「あ、服部君。和葉ならさっき、小嶋先生が来て一緒にどっか行ったよ。」 「ほーか、おおきに。」 礼を言いつつ、顔が引きつっていく平次。 欠席だと思い、また和葉に届け物をさせるつもりの小嶋の行動は平次に大きな不信感を抱かせた。 平次は心当たりの場所を思い浮かべる。 職員室・・・数学準備室・・・体育館・・・部室・・・ 和葉を見つけるために動き出した長い足は、あせる気持ちとともにどんどん速まり、帰宅する生徒でざわめきあう廊下を走り抜けていった。 探していたその声は、数学準備室のドアの向こうから聞こえてきた。 呼吸を整え、気配を消し様子を探る平次。 その目は、凶悪犯を追い詰めている探偵のものになっていた。 「じゃあ先生、この問題は?」 「これは、こっちの公式で・・・って。だいぶ前にやった所だよな? わかってなかったのか、遠山?」 「・・・・・」 「よし、お前はこっちのプリントも宿題追加な。明日見せにこいよ。」 聞こえてきたのは教師と生徒の普通の会話。 しかし平次の拳は怒りで握りしめられ、ふるふると小刻みに震えていた。 落ち着くために何度か深呼吸をした、数秒後。 すごい勢いでドアを開け、仁王立ちで2人を睨みつける。 「キャー!・・・な、何や平次・・・びっくりさせんといて。」 「おいおい服部。どうしたんだ、いったい?」 「フン。お前らこそ、こんな所でコソコソ何やっとるんじゃ。」 「何って? アンタがおらんかった時のプリント受け取りに来たついでに 教えてもーただけやん。」 「やったら職員室でやればええやろっボケェ!こんな校舎のはずれの準備室やなくて!」 「服部、お前何の心配してるんだ?ここは学校だぞ。考えすぎだ。」 苦笑しながら話す小嶋に、そこに和葉がいることを忘れキレる平次。 「だいたいアンタ、滅多に人が来ないさびれた準備室に、生徒連れ込むっちゅーんはどーいうこっちゃ!」 「だから、たまたま服部に渡してもらうプリントをこっちに忘れたから 一緒に来てもらっただけだろ。」 「それが怪しい言うとるんや。だいたいアンタがコイツに向ける視線の中に、何が込められてるかなんて、こっちはとっくに気づいとるんじゃ!」 「そーか、さすがは名探偵だな。だけどまだ、どうこうするつもりはないよ。 生徒だしな。」 「まだって、どういうつもりや。」 「まだはまださ。時期がきたらって事だよ。」 「そんな事させるかっちゅーんじゃ!」 「あれ?今の服部にそんなこと言う権利はないだろ?」 「・・・・・クソッ・・・・・」 悔しそうに顔をそむける平次。 「あのー?何の話しとるんですか?主語ないし、まだだとか権利がどーのとか?」 「「・・・・・・・・」」 突然の和葉の声に黙り込む2人。 当の和葉は、自分のことを言われているとは気づきもせず不思議そうな顔をしている。 気まずい空気が漂い始めた準備室で、再び和葉が口を開いた。 「じゃ、先生。平次にプリントやらせて、明日アタシの宿題と一緒に持ってきます。」 「そうだな。2人ともちゃんとやるんだぞ。」 「はーい。また何かあったらメールしてくださーい。」 「・・・・・」 「オイ、メールって何や!オマエ、小嶋とメールのやり取りなんぞしとるんかっっ!答えろ!」 「あーあ、遠山。だからメールのことは内緒にしとけって言っただろ。大騒ぎになるのは目に見えてるんだから・・・」 「・・・・えっと・・・平次?2年になってクラスが別になったやん。でも休んだ時のプリント届けるんは、一番近所のアタシの仕事やねん。んで、届けもんとかある時に先生から連絡もらうんよ。それだけやん。」 「それだけやって?当たり前じゃっ!」 「あ、あと一年の時は欠席の連絡やとか・・・ まぁ、とにかくメールは平次がらみのばっかりなんよ。」 「一年の時からやと?小嶋ァ!何やっとんじゃー!!」 「・・・・・遠山はウソも方便って言葉、よく理解したほうがいいな。正直すぎだぞ。で、服部。自分のクラスの生徒の、特に行動が把握できないお前の状況を知るのも担任の仕事だ。服部のことなら遠山に聞くのが一番だからな。」 確かに小嶋の言うことは、担任として正しい。 それは平次にも理解出来た。 しかしそれを口実に、小嶋がひそかに想いを寄せている和葉とメールのやり取りをしているという事実は、とても許せるものではなかった。 それが、たとえ平次の為であっても、だ。 平次は小嶋を睨みつけ、無言で和葉の腕をつかみ、引きずるようにして準備室を出た。 一言も喋らず、ただ前方をまっすぐ見て早足で歩き続ける。 和葉は何もわからないまま、ただ、ひどく機嫌の悪い平次に強くつかまれ痛む腕が、少しでも楽になるよう、彼の歩調にあわせ小走りでついて行った。 辺りは今の平次の心を表すかのように、徐々に暗くなっていった。 どのくらい歩いただろうか。 落ち葉をクシャッと踏みつけた音にハッとして、ようやく立ち止まり周囲を見回すと、そこは家の近くの、幼い頃よく遊んだ公園の入り口だった。 薄暗い公園に立ち入ったものの、昔を懐かしむ状況ではない。 何をどう言って良いのか・・・ 平次の心は乱れたまま無言で立ち尽くす。 そんな平次の様子を横目で見ながら和葉もまた、かける言葉が見つからず、俯いていた。 つかまれた腕はほどかれることなく、いつもより近い距離にいるのも2人は気づかなかった。 平次がやっと口を開いたのは、それから随分時間がたってからだった。 「小嶋からのメール見せろや。」 「は?何で?」 「うっさい、ボケ!とっとと出せっ!」 「んもー、しゃーないなぁ・・・他のは絶対見んといてよ!・・・・ハイ。」 『服部がどうしているか知ってるか?』 『そうか、ありがとう。遠山も大変だな。待ってばかりでつらくないか?』 『待ち疲れたら、グチでも何でも聞くぞ。』 『遠山も無理するなよ。』 『服部は好きでやっている事だからいいが、遠山の方が心配だ。 いつもお前のこと気にしてるんだぞ?』 『今度気晴らしに、どこか連れて行ってやろうか?』 ・・・・・いくら鈍感な和葉とはいえ、これらのメールを見て何も感じなかったのだろうか? 言葉の裏に隠れる小嶋の気持ちが見えてくる。 こんな状況になっている事に、全く気づいていなかった平次は思わず俯き、唇を噛み締めた。 平次に対して、直接言葉に出したわけではないが、自分の気持ちを認めた小嶋。 本音を滲ませたあの数々のメールを、もう二度と和葉に送らせない為にどうするべきか、平次は迷っていた。 いや、本当はわかっていたのだ。 和葉が何かを感じ取る前に、小嶋と決着をつけるしか方法は無い事を。 何かを決心し、ようやく顔を上げ和葉の様子を伺いながら口を開いた。 「なぁ和葉。オレに内緒で、小嶋とメールのやり取りしとって楽しかったんか?」 「へ?楽しいとかいう内容やないやろ?連絡だけやん。」 「教師との連絡メールやなくて、オマエと小嶋っちゅう男がメールのやり取りしとって、どうやったか、ちゅうことや。」 「ちょ、平次?ますます意味わからんよーになってしもたよ?何なん、いったい・・・」 小嶋からの好意に全く気づいてない和葉にとって、平次からの問いかけは、難しい謎かけにしか思えなかった。 「ほな、小嶋からメールもろて嬉しかったんか?」 「は?やって先生からメールもろた時って、平次が事件がらみで休んでる時ばっかりやん。やったらむしろ、平次から事件解決して無事やっちゅうメールもろた方が、よっぽど嬉しいんやけど?」 その言葉でささくれ立っていた平次の心は、だんだんと落ち着いてきた。 そして大きな溜息を1つつき、和葉をまっすぐに見た。 「ほんなら小嶋からのメール、待っとった訳やないんやな?」 「あたりまえやん!」 「やったら和葉。これからはオレからのメールだけ待っとけ。」 「平次からのメール?」 「そーや。オレだけ待っとけ。」 「オレだけって・・・メール?それとも平次を待つん?」 「オレや、オレ。オレを待っとけ。したらオマエんとこ戻ってくる。」 「・・・え?・・・」 「オマエは10年でも20年でも、この先ずっとオレのことだけ考えとったらええんや。オレやってこれからも、ずっとオマエの事だけ考えるんやからな。」 「平次・・・それって・・・」 「オマエはもう、小嶋なんかとメールすんなっ。オレから言うとく。」 「うん・・・平次。ずっと、ずーっと一緒なんやね?おじいちゃんとおばあちゃんになっても?」 「おう。」 平次の真剣な瞳と、真っ赤になった和葉を見れば、大切な言葉はなくても、これで十分だった。 17年間、当たり前のように一緒に過ごしてきた二人にとって、これからも共に過ごす為の大事な一歩を、今、ようやく踏み出した。 さっきまで、あんなに強く和葉の腕をつかんでいた平次の大きな手は、今度は優しく和葉の小さな手を包み込み、ゆっくりと2人は歩き出した。 和葉の腕の痛みはつながれた手の暖かさで、すっかり気にならなくなっていた。 翌日の放課後。 平次は1人で小嶋の元を訪れた。 「おー、服部。昨日あれからどうした?遠山からプリント受け取ったんだろ?」 「もうアイツに関わんなっ!」 「どういうことだ?」 「アイツはオレの女になった。もう2度とメールとかするんやないで!オレのことはオレに聞け。」 「ふーん、昨日あれから・・・?俺の存在が2人を後押ししちゃったのか・・・ちょっと行動早まったかなぁ。」 「うっさい!アンタ教師やろ!生徒相手に何考えとるんじゃ。」 「大したことはしてないよ、もちろん。後は卒業後にじわじわといくから。ま、覚悟しとくんだな。」 「てめっ、ふざけた事ぬかすんやないで!」 「服部があの子を、しっかりつかまえておけばいい話だ。ずいぶん鈍感みたいだし、振り向かせるのは大変そうだな。」 「フン。アイツの相手は昔も今もこれからも、オレしか出来んのや。よく覚えとけ。」 そう言い捨て、平次は小嶋に背を向け歩き出した。 やっと手に入れた和葉に悪い虫がつかないように、これからも今まで以上に苦労することは目に見えている。 しかし2人で歩き続ける未来の為に、全ては和葉に知られる事なく終わらせなくてはならない。 誰もいない廊下でふと立ち止まり、平次は決意を新たにした。 「アイツが、ちーとは自覚してくれとったら楽なんやけどな。」 そんな独り言がもれてくるが、先程と比べ表情は明るい。 和葉に何も言わず教室を飛び出したので、今頃きっと、カバンだけを残していなくなってしまった平次を心配しているだろう。 どことなく緊張していた身体の力をフッと抜き、窓の外を見上げた。 「・・・和葉・・・」 小さく呟き、平次はオレンジ色に染まった廊下を、和葉の元へ走り出した。 終 |