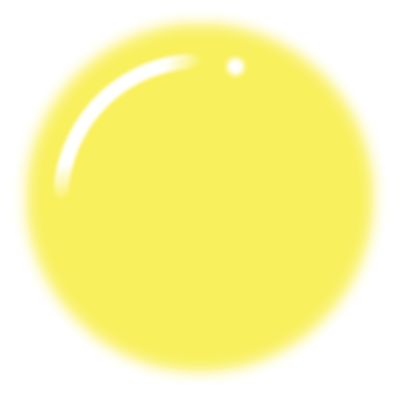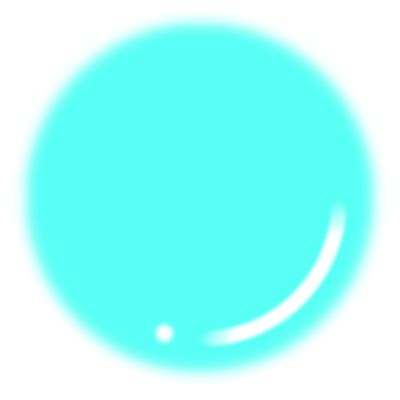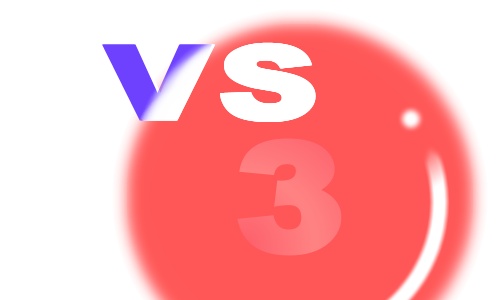| 見上げた空が随分と高くなり、視界を赤とんぼがスーっと横切った。 何をするのも気持ちの良い季節。 スポーツの秋。 読書の秋。 食欲の秋。 そして季節の変わり目となり、体調を崩しやすくなって・・・・ ここ改方学園高校の保健室に、1人の教師がやってきた。 「あら、小嶋先生。どうしはったんですか?」 「すいません、頭痛薬いただけますか?」 「ただの頭痛ですか?」 「んー、しばらく睡眠不足気味で鼻もグズグズしてたから、珍しく風邪みたいです。」 「そうですか。はい、お薬・・・・ほな、しばらく休んでいきます?」 「そうですねぇ、3,4時間目は授業ないですけど。」 「今休んどる生徒が2人いますので、ベッドは使えませんけど、ここでゆっくりしとって下さい。」 「はぁ。」 「私はちょっと職員室で仕事があるので、留守番してもろてええですか?」 「そういうことですか。」 「休んどる生徒達はぐっすり寝てますけど、もし起きて教室に戻るんやったら、 そのまま行かせて構いませんから。ほな、お願いします。」 「わかりました。」 保健医が部屋を出て行き、静かになった部屋で小嶋は大あくびをした。 3時間目が始まり、午前中ののんびりした時間帯。 日当たりのいいこの部屋は、ざわめきあう職員室とは違い、ゆったりとした空気が流れ、 2人の生徒が休んでいる事さえ、つい忘れてしまうような穏やかさだった。 徐々に薬が効いてきたようで、ぼーっと空を眺めていた小嶋も、ついウトウトしかけた時。 生徒が休んでいたベッドがきしむ音がして、人の気配を感じた。 それまで白一色だった部屋の一角のカーテンが開かれ、寝癖をつけたままの一年男子が 上履きを履きながら出てきた。 「あれ、小嶋先生?」 「おう、俺は留守番だ。気分はどうだ?」 「さっきより随分良ぉなったんで戻ります。」 「そうか。」 生徒に近づいた小嶋は、もう1つのカーテンのしまったままのベッドに、ふと目をやり 目を見開き固まってしまった。 カーテンの下から見える上履きには、「3−A 遠山」とあった。 呆然としてそれを見つめていると、遠くで男子生徒の「ありがとうございました。」の 声が聞こえた。 「と・・・・遠山なのか・・・・?」 恐る恐るカーテンを少し開き、覗いてみる小嶋。 そこは足元だったようで、人が寝ているふくらみは見えても、肝心の顔は見えない。 一歩足を踏み入れ、あわててカーテンを閉めた。 そこはカーテンに仕切られただけの、頼りない、でも確かに2人きりの狭い密室が出来上がっていた。 掛け布団にかくれ、顔はまだ見えない。 ただ枕の横には、紅葉色のリボンが置いてあるだけだった。 もう一歩近づく。 さらりとした長い髪が見える。 その時。 「う・・・・・・んぁ・・・・・・」 思わず別のことを想像して、ドキっとしてしまうような声がして、その人物は寝返りをうった。 ハッとした小嶋は、自分がかなりベッドに近づいていた事に気付き、あわてて一歩下がった。 小嶋の目には予想にたがわず、期待どおりの瞳を閉じた彼女の横顔が写った。 ゆっくりと呼吸にあわせ、掛け布団が上下している。 そおっと、壊れ物を扱うかのような丁寧で優しい動きで、和葉の額に手をやった。 「・・・・38℃、くらいか?」 小嶋は小さな声で呟き、額にやったその手で、頬をつつみこんだ。 なんとなく和葉の表情が微笑んだような気がして、寝息を確認するため耳を近づけた。 スースーという、和葉がそこにいる証の穏やかな寝息。 ふと見ると、憧れていて夢にまで見た、そして今は憎いあの男のものである 彼女のふっくらとした唇がそこにあった。 ゴクリ 生唾を飲み込む音が、やけに大きく自分の耳に届いた小嶋。 ギクリと動きを止めて、他に誰もいない狭いカーテンの中を見渡した。 そして。 彼の理性を一瞬でぶち壊してしまった、桃色の柔らかそうなその唇に 無意識のうちに引き寄せられ、小嶋は自分のそれを近づけていった。 カーテンの外では、相変わらず穏やかな日差しが差し込み、 校庭で体育を行なっている生徒の掛け声が、遠くから聞こえてくる。 「お前の風邪をもらってやる・・・・」 そう小さく呟き、小嶋は唇を重ねた。 しばらくそっと触れていただけだった唇はやがて、ほんの少し離れた。 「とお・・・や・・・ま。・・・・・好きだ。・・・一年の時から・・・好きだった。」 その声は和葉の耳にだけ届き、再び唇が重ねられた。 そして、未知の世界である彼女の中に侵入しようと、彼の舌が動き出した。 固く閉じられた和葉の唇を割って、中に入る事がなかなか出来ず、 小嶋がイラつき始めた時。 それまで全く動かなかった和葉が、イヤイヤをするかのように顔を左右に振り、 背を向けるように寝返りをうった。 ビクっとして動きを止めた小嶋は、自分のしてしまった事に驚愕して 逃げるようにカーテンの外に出て呟いた。 「お・・・俺は・・・・。遠山に・・・・。」 小さく震える腕を押さえつけるように腕を組み、あわてて保健室を出て俯いたまま 誰もいない廊下を早足で歩いていった。 そんな小嶋の後姿は、いつもの堂々としたものではなく、やけに小さく見えた。 その頃、ベッドに横になったままの和葉は大きな目を見開き、 小嶋に狙われて赤みの増した唇を押さえていた。 「先生が・・・・キス?・・・・アタシに・・・・」 和葉は誰かに優しく頬を包まれた時、目を覚ましていた。 「38℃くらいか」の声を聞き、そこにいるのが小嶋だと気付いたが、 間近にあるその気配に驚き、目を開く事が出来ずにいた。 「好きって・・・・・アタシを?」 いくら鈍い和葉といえども、目の前で言われた言葉の意味を間違えることはなかった。 そして、今までの小嶋から向けられた言葉の数々、様々な行動の意味を ついに理解してしまった。 平次が事件でしばらく居ないときにもらった「大丈夫か?」のメールも、 夏休みに東京に行くのに付き添ってくれると言ったその言葉も、 全てそういう意味があったのだと。 今まで恋愛の対象として見てこなかった小嶋のあの行動に、和葉は激しく動揺していた。 でも、1つだけ確実にわかった事。 それは。 平次に知られてはいけない。 元々険悪だった小嶋と平次の間を、これ以上こじらせる事は出来ない。 険悪だった原因は自分だったとは気付かずに、和葉はその事だけを心配していた。 校庭から聞こえてくる、「ありがとうございました。」の声。 間もなく3時間目が終る。 きっと平次は保健室に来るだろう。 和葉は平次の前で不自然にならないように、無理に笑顔を作ってみた。 そして終了のチャイムが鳴りしばらくすると廊下がざわめき出し、保健室のドアが開いた。 耳に馴染んだ聞きなれた足音がして、平次が姿を見せた。 彼には似合わない静かな動きで、カーテンをそっと開ける様子を見て、 和葉はぎこちなく笑顔をつくった。 「起きとったんか?」 「うん。」 「熱はどーや? 大丈夫なんか?」 「少し寝たから、さっきより気分よーなったよ。」 和葉の額に優しく手をやる平次。 さっきの小嶋の行動を思い出しドキっとした和葉は、平次のその手を取り指を絡ませた。 いつものぬくもりにホッとする。 「しばらく手ぇつないどって。安心する・・・・」 「なんや、こんな時だけ甘えよって。」 テレながらも、そこにあった折りたたみ椅子を開き座り込む平次。 頼りないカーテンで仕切られただけのベッドは、先程とは違い、穏やかで優しい密室になった。 つながれた手の温もりに安心した和葉の目は、自然と閉じられていった。 そんな様子を優しげな表情で見つめ、つながれた手を口実に、 平次もまたベッドにつっぷして眠ってしまった。 しばらくして戻ってきた保健医は、改方名物の2人の姿を見つけると、 クスリと笑い黙ってカーテンを引き、仕事を始めた。 4時間目が終わり早退することにした和葉は、平次に支えられながら廊下をゆっくり歩いていた。 教室に戻るため、曲がった所で誰かとぶつかり、3つの声が重なった。 「うおっ!」 「きゃっ。」 「あっ!」 体に力が入ってなかった和葉は、ぶつかった衝撃でふらりとよろけた。 それを平次があわてて支える。 「気ィつけろや、オイ!」 「あぁ、すまない。大丈夫か?」 聞き覚えのあるその声に顔を上げ、お互いに良く思っていない相手だとわかると 2人は顔をしかめた。 心の中で舌打ちをしつつ、いつも通り小嶋は和葉に声をかけた。 「どうした、遠山? 大丈夫か。」 俯いたままの和葉は、その声に思わずビクッと反応してしまった。 その様子に平次はビックリしたように和葉を見つめる。 顔を上げずに和葉は小さな声で答えた。 「はい。大丈夫です。 ・・・・・平次、早よ帰りたい・・・・」 「お、おう。」 和葉は平次を促し、ふらつきながら足を踏み出した。 平次は小嶋を振り返り、何か言いたしげな視線を投げかけたが、すぐに和葉を支え立ち去った。 その後ろ姿を見送りながら、小嶋は和葉が全く自分を見なかったのに気付いていた。 「まさかな・・・・」 あの時理性を失い、目の前で眠っている彼女にしてしまった行為。 気付かれているはずは無い。 眠っていたのだから。 そう自分自身に言い聞かせ、つい俯いてしまう顔を無理やり上げた。 口元にはいつもの微笑を貼り付け、前を向き歩き出した。 一方平次は早退する和葉を送るという口実で、同じく早退手続きをし、 よろける和葉を支えながらゆっくり歩いていた。 2人はさっきから無言のままだ。 先程から黙ったままの平次には気になることがあった。 それは廊下の角で小嶋とぶつかった時の和葉の反応だった。 今までどんな時でも、小嶋には愛想が良かった和葉。 それが無意識で行なわれているのを知っている平次は、腹が立つものの やめろ!と強く言えないでいた。 和葉は小嶋の気持ちを知らないのだから。 そんな和葉が、小嶋の声にビクッと反応し最後まで顔を上げなかった。 それは熱のせいだけでは無いような気がする。 思い切って平次は声をかけた。 「おい和葉、大丈夫か? 歩くのしんどくないか?」 「・・・・・うん。だるいけど平次おってくれるから大丈夫。」 「しゃべんのはどうや?」 「んー、まぁ、なんとか。」 「ほーか・・・・ほなオマエ、さっき廊下で小嶋とぶつかった時、態度変やったな?」 あの時、思わず小嶋の声に反応してしまった事を、平次に気づかれたか不安だった和葉。 やっぱりな・・・・と内心で冷や汗をかきつつ平静を装った。 「んー? ・・・・ぶつかったんやっけ?アタシ・・・・」 「おう。小嶋にな。」 「・・・・ぼーっとしとったから、解らんかったなぁ・・・・」 「ほーか? オマエ、ビクッとしとったぞ。」 「・・・寒気・・・したんやない?」 口調だけ聞くと、落ち着いて受け答えしているようだが、俯き気味の和葉の視線は 足元で落ち着きなく動いていた。 その表情は平次からは見えていない。 和葉もまた、平次の表情は見えていなかった。 和葉の髪を束ねる揺れるリボンを、射抜くような強い視線で見ていた事を。 これ以上聞いても、今は答えられないだろう。 平次はそう判断して、和葉を支える腕に力をこめた。 「・・・・・ほな、家まであと少しや。頑張るんやで。」 翌日、和葉は学校を休んだ。 和葉の態度がおかしい。 必死に隠そうとしていても、2人の歴史が和葉の異変を告げている。 そしてここ1年、特に恋人としての親密なつながりがある平次には、和葉の不自然さが 気になって仕方が無い。 小嶋とぶつかり、声を掛けられた時のビクッとした様子。 あれは寒気などではないのは、すぐわかった。 では何に・・・・・ そんな事を考えながら授業を受けていても身につくはずもなく、平次は体調が悪いと 保健室に向かった。 「あら、服部君。どうしたん? 昨日あれから遠山さんはどうやった?」 「和葉ならまた熱上がってな、今日は休んどる。」 「そう・・・・・心配やね。」 「昨日アイツ、1時間目終ってからここに来たんやっけ?」 「そーやね。あと1年男子もおったけど、彼は途中で戻ったみたいやね。」 それを聞き平次は、来室者が記入する表をパラパラとめくった。 「先生はずっとここにおった?」 「途中1時間くらい職員室に用があったから・・・・」 「その間、ここは休んどった奴らだけか?」 「あぁ、それなら小嶋先生が頭痛薬欲しいっていらしたから、ついでに留守番頼んだけど?」 平次の表情が変わった。 「小嶋やと!? 」 「そうやけど?」 「・・・・・・・なるほどなぁ、先生おおきに。ほな行くわ。」 熱を出し、保健室で眠っていた和葉。 そこに薬をもらいに来た小嶋。 そこで2人に何かが起こった。 和葉が小嶋の声を聞き、ビクつくような何かが・・・・・ 平次はどこかに寄った後、小島の元に向かった。 「よぉ、アンタに話があるんやけど。」 「何だ、服部?」 誰もいない印刷室で向き合った2人。 今にも掴みかかりそうな平次と、落ち着きはらっている小嶋。 「アンタ、和葉に何をした?」 「オイオイ、またか服部。 何のことを言ってるんだ?」 「和葉が眠っとった保健室に、アンタは薬をもらいに来た。保健医は職員室に行って、 もう1人おった1年坊主は途中で教室に戻った。本人に確認済みや。」 「ほぅ。」 「そんで、アンタと和葉が2人っきりになった。」 「・・・・・・・」 「その後、廊下でアンタとぶつかった時、和葉はアンタの声を聞いてビクついた。」 「だから何の事だ?」 平次は自分より背の高い小嶋の胸倉をつかみ上げた。 「アンタ、和葉にイタズラしとったんか!?」 「・・・・・イタズラって・・・・・そんな訳ないだろ!」 「オレとしては不本意やけどな、和葉はアンタの事を信用しとった。その和葉がアンタの声で ビクついたんや。アンタに無理矢理何かされたんかって思うに決まっとるやろ!!」 「毎度毎度、お前の言い掛かりには驚かされるな。いくらなんでも保健室でそんな事する訳 ないだろ。いい加減にしろ!」 小嶋は平次の腕を振り払い、上着を直した。 「ほーか。なら和葉問い詰めた方が早そうやな。何かしとったらタダじゃすまんぞ。 顔洗って待っとけや!!」 そう吐き捨て平次は印刷室を出た。 そのまま、モヤモヤした気持ちを発散させるかのように学校を出て、和葉の家に向かって 走り続けた。 出来れば和葉をきつく問い詰めるような事をして、逆に小嶋を意識させるような事はしたくない。 和葉・・・・・・・・・和葉・・・・・・・・・和葉・・・・・・・・・ (オマエは小嶋に何かされたんか・・・・・) 平次の走り抜けるスピードは一層上がり、落ちていた枯葉がフワリと舞い上がった。 その頃、メールの着信音で目を覚ました和葉は、ぼんやりしつつも枕元の携帯を手に取った。 差出人の名前を見て動きが止まる。 「せ、せんせ・・・い・・・」 これまで、あんなに心の支えにしていた名前を見て愕然とした。 気が重いながらも、ゆっくりと携帯を開く。 『 すぐ削除しろ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あの時、起きていたのか?』 和葉の心臓は、外にまで聞こえてしまうくらいバクバクといいだした。 ガタガタと震えだした手ですぐに削除して、布団をかぶり小さく丸くなった。 (ど-しよう、ど-しよう、ど-しよう・・・・・) 和葉は平次が小嶋の元を訪れた事を察し、そして、昨日の事を問い詰めるために もうすぐここに来るであろうと、簡単に予想ができてしまった。 平次に秘密を持ってしまった和葉は、嘘を吐き通す事が彼のためになると信じ 昨日からずっと考えていた理由「熱で覚えていない」を、うわ言のように繰り返した。 しばらくして、玄関の鍵を開ける音がした。 ・・・・・・深呼吸をして震えを止める和葉。 階段を上ってくる足音がする。 ・・・・・・笑顔を作る。 ドアが静かに開かれた。 「へーじ!」 満面の笑みで平次を出迎えた和葉。 「おぅ。起きとったんか。気分はどーや?」 「うん、大丈夫。平次、学校さぼったん?」 「あー、まぁな。オマエ心配やったし・・・・・」 「ありがと。昨日の夜は随分上がったけど、今は下がってきた。」 「ほーか。」 平次はゆっくりと和葉から視線を外した。 和葉はそんな平次をずっと見つめている。 「・・・・・そんで・・・・・オマエ、昨日の事やけどな・・・・・」 「んー? 何?」 平次は言いにくそうに口を開いた。 「・・・・・やから、な。・・・・・小嶋とぶつかった時にな・・・・・」 「ぶつかったって・・・・・いつやっけ?」 「オマエと保健室出て、歩いてるときや。」 「んー?・・・・・そんな事あったっけ?」 「オマエ、あん時おびえるようにビクついたやろっ!」 「え? 何のこと? アタシ知らんよ。」 「オマエ・・・・・・まさか覚えとらんのか?」 「覚えとらんって言われても・・・・知らんよ?アタシ。」 「・・・・・・・・・・」 平次は和葉の答えに、脱力して座り込んだ。 「オマエ、昨日一日の行動話してみ?」 「はぁ? さっきから何やの、一体??」 「ええから!」 「んーっとなぁ、朝から少し熱っぽいかなぁって思ったんやけど、試験前やしな頑張って行ったんよ。でもやっぱりダメで、1時間目終って保健室行って休ましてもろた。」 「ほんで?」 「寝てたら平次来てくれて、手ぇ握って大丈夫かって言ってくれたやん。」 「・・・・・・」 「あとは・・・・・夜おかあちゃんが、おかゆさん作ってくれたけど、ちょっとしか食べれんかった。」 「他には?」 「えー、そん位かなぁ?今朝になったら、熱も随分下がってお腹すいとったよ。」 「ほーか・・・・・」 「あ、お父ちゃんがな、このヒエピタとアイス買うてきてくれたんよ。アイスまだあるはずやから 平次食べてええよ。」 和葉は覚えていない。 和葉は、昨日の出来事の大部分を、覚えていない。 「なぁ平次、いっぱい心配してくれとったなぁ、おおきに、な。」 嬉しそうに笑う和葉が、どこかしら遠くに感じた平次。 大事な事は何も覚えていない和葉。 のらりくらりとかわしていく小嶋。 もう聞けない。 和葉は何も答えられない。 ・・・・・この疑惑は晴れないままだと思い、平次はぎゅっと目を閉じた。 和葉が覚えていない位だから、和葉の身には何も起こっていない。 平次は自分自身にそう言い聞かせ、無理やり納得しようとしていた。 しかし、そう思えば思うほど平次の心は灰色になるばかりだった。 小嶋が和葉に・・・・・ 小嶋は和葉と・・・・・ 小嶋と和葉が・・・・・ 大きな不安と疑惑が渦巻くまま、平次は和葉をじっと見つめた。 その日の夜中。 和葉は小嶋のメールに返信した。 『起きてました。』 すぐに返ってきたメールには、 『卒業後に返事聞かせてくれ。』 とだけあった。 「平次・・・・・ごめん・・・・・」 と小さく呟き、和葉は静かに涙をこぼした。 END |